社会福祉法人キャリソル会
アクセス東京都/練馬区/豊玉中 2丁目34ー5
企業情報
クチコミ
インタビュー
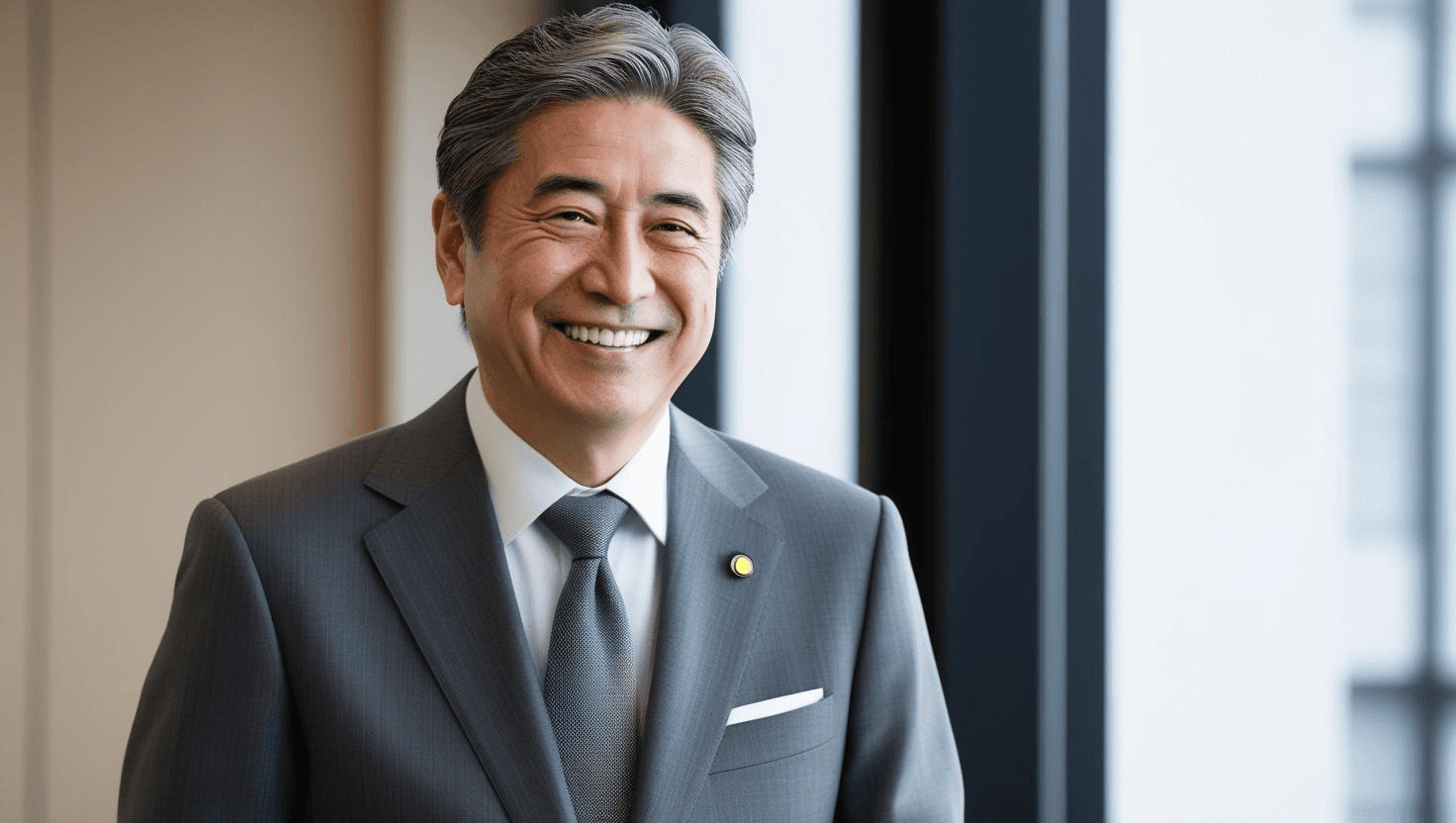
1963年創業の社会福祉法人キャリソル会特別養護老人ホーム「キャリソル園」 1995年に31歳という若さで父親から事業を継承。 継承から30年たった今の気持ちや今後の展望を代表取締役社長「喜谷 荘」様インタビューを行いました。
介護業界に興味を持ったきっかけを教えてください
父親が老人ホームの創設者だったので、子供の頃から施設に遊びに行くこともあり、老人ホームが当たり前の存在でした。
明確に後を継いでくれと言われたことはありませんが、 一人っ子だったのでいずれ事業を引き継ぐのかなとは思っていました。
利用者さんも職員さんたちにもいつも良くしてもらっていたので、自分もここを守るんだ!大きくするんだ、といった使命感のようなものを感じているときもありました。
父には「経営者として人を動かすのであれば自分がなにより詳しくなっていないといけない、良いも悪いも現場をしっかりと知っているべきだ」と常日頃から言われており、自分も良くしてくれたホームの人たちの助けになりたいと介護士の資格を取り、まずは新入社員として現場で働くことから始めました。
始めに介護士として働き、業務の流れを覚えたり、採用に関わったりしていました。
そこから、徐々に全体をみていくような役割を担っていきました。
その後少しずつ法人運営の部分を学んでいきました。
理事会関係や実地指導のことなど、施設の運営に関わるさまざまなことをやりながら、全体の運営を覚えていったという感じです。
事業を継承したときのお気持ちを教えてください
小さい頃、老人ホームは“もう一つの家”でした。父の背中と、たくさんの笑顔があった場所です。
私はこの老人ホームで育ったようなものです。
保育園の帰りに父に連れられて立ち寄ったり、休日には施設のラウンジでおやつをもらって、ご入居者の方と一緒に折り紙をしたり、将棋を指したり。職員さんが優しく声をかけてくれて、時にはおんぶしてくれることもありました。
年配の方たちの柔らかい笑顔、廊下に響く楽しそうな会話、食堂からふわっと漂ってくる煮物の匂い。
そうした一つひとつが、今でも記憶の中ではっきりと思い出されます。
あの頃の私は、“ここは特別な場所”だとは思っていませんでした。ただ、安心できて、あたたかくて、誰かがいつも笑っている場所——それが、私の中の“老人ホーム”というイメージの原点です。
けれど、いざ働き始めると介護の現場の大変さや経営の難しさも目にするようになり、次第に「継ぐ」ということの現実が見えてきました。
正直、最初は葛藤もありました。父のようにできるのか、自分にできることがあるのか、自信が持てない時期もありました。
ただ、迷っていたとき、ふと小さい頃に感じていた“空気”を思い出したんです。
優しい声、手のぬくもり、みんなが家族のように過ごしていたあの空間。
それを思い出したとき、胸の中に自然と「守りたい」「引き継ぎたい」という想いが芽生えてきました。
そして父から正式に事業を引き継いだとき、自分の中で何かが動き出した気がしました。
父はいつも「この仕事は、人の人生の一部に関わらせてもらっているんだ」と言っていて、その言葉の重みが今、ようやくわかるようになりました。
これからは、父が築いてきたものを大切にしながらも、私なりの視点で新しい風を吹き込んでいきたいと思っています。
時代は変わっていきます。でも、人が“人らしく”最期まで暮らせる場所をつくるという本質は、きっと変わりません。
あの頃、子どもだった私が感じていた“安心”や“あたたかさ”を、今度は私が誰かに届けられるように。
そう願いながら、毎日この場所に立っています。
大切にしている経営方針は何ですか
利用者一人ひとりの“人生の物語”に寄り添うことを大切にしています。
老人ホームの経営において最も大切にしているのは、「その人らしさ」を尊重する姿勢です。
ただ“安全に過ごせる場所”を提供するのではなく、ご入居者のこれまでの人生、価値観、好きだったことや大切にしているものをきちんと理解し、それに基づいたケアやサービスを心がけています。
職員にも「介護をする人、される人」という関係ではなく、「人生のパートナー」という意識を持つよう伝えています。だ
からこそ、日々の会話や表情、些細な変化にも敏感になり、心の通ったサポートができるのだと思っています。
そしてまた職員たちの「人生の物語」も大切にしなくてはなりません。
経営的にも効率や利益だけを追うのではなく、「ここに入ってよかった」とご本人もご家族も心から思えるような施設づくりを目指し、
職員一人ひとりの現場の声を大切にする運営を心がけています。
特徴的な社内制度はありますか?
職員の声を反映する制度”と、働き方の自由度を重視しています。
私たちの施設では、職員の意見や声をできるだけ反映させるための制度を導入しています。
たとえば、定期的に「職員意見交換会」を開催して、経営陣と現場のスタッフが直接意見交換をする場を設けています。
現場で働いているスタッフの声こそが、サービスの質や施設の運営をより良くするために不可欠だと考えています。
そのため、フラットな意見交換をする機会を大切にしています。
また、最近では「フレックスタイム制度」を導入しました。
介護という仕事はどうしてもシフト制になりがちですが、職員のライフスタイルや家庭の事情に合わせて柔軟な働き方ができるように、出勤時間や退勤時間を自分で調整できるようにしています。
この制度によって、育児や介護をしている職員が自分の時間を持ちながらも、仕事にしっかりと取り組むことができる環境を提供しています。
さらに、健康面を支援するために「ヘルスケア手当」も導入しています。
これは、職員がジムに通ったり、健康診断を受けたりするための費用の一部を支給するもので、心身ともに健康でいることが、良いケアに繋がるという考えから導入しました。
私たちは、職員がやりがいを感じ、長く働き続けられる環境を整えることが、最終的にご入居者の満足度にも繋がると信じています。
そのため、職員の働きやすさを最優先に考えた制度をこれからも増やしていきたいと思っています。
今後の展望を教えてください
人生の最期まで、“その人らしさ”を支えられる施設でありたいと考えています。
これからの時代、老人ホームは単なる“介護の場”ではなく、その人の人生の最終章をどう豊かに、
そして穏やかに過ごしていただくかという視点がますます重要になってくると思います。
私たちが目指すのは、ご入居者一人ひとりの生き方や価値観を尊重し、その人らしい時間を最期まで支えていける施設です。
特別養護老人ホームですので、日常のケアという視点においても、医療的な管理だけでなく、ご本人の「こう過ごしたい」「こういうことが好きだった」という声に耳を傾け、可能な限り希望に寄り添った支援を行っていきたいと考えています。
たとえば、昔の思い出の曲を流したり、好きだった食事を楽しんでいただいたり、ご家族との時間をゆっくり過ごせるよう環境を整えるなど、「小さな幸せ」を大切にするケアに力を入れていきたいです。
もちろん、医療との連携も欠かせません。
看取りの場面では、外部の医師や訪問看護師との協力体制をより強化し、ご本人だけでなくご家族の不安や悩みにも丁寧に寄り添う姿勢を大切にしていきます。
命の最期に関わるからこそ、施設としての在り方が問われる瞬間でもあります。
さらに、地域に根ざした施設づくりも今後の大きな目標です。
ご入居者だけでなく、地域の高齢者やご家族、子どもたちまで、世代を越えて人が集い、関わり合える場所にしていきたい。
たとえば、地域交流イベントや認知症カフェ、介護予防教室などを通じて、「ここがあるから安心」と思っていただける拠点づくりを目指します。
そして何より、職員一人ひとりがやりがいと誇りを持って働ける環境づくりにも注力していきます。
人材不足が叫ばれる中、ICTや介護ロボットなどの活用と、スタッフへの教育・メンタルケアを両立させ、長く安心して働ける職場にしていきたいと思っています。
最後までその人らしく、そして笑顔で過ごせる場所。
そんな老人ホームであり続けることが、私の願いであり、これからの展望です。